■■■ 2005-02-05 ‖Sat‖ ■■■
 その名にちなんで
その名にちなんで
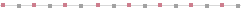

もともと処女短編集の「停電の夜に」でその丁寧で繊細な文章に魅せられていたということもあって、かなり期待して読んだ。アメリカに移民してきたベンガル系の夫婦にやがて子どもができ、その子どもが大きくなって大学に進学し就職し、そして結婚する。長い時の流れのその時々の情景を丁寧に、でも過剰ではなく静かに描き込んでいた。何となくエイミ・タンの「ジョイラック・クラブ」を思い出す。こちらは4人のアメリカ移民である中国女性たちがその生き様を振り返るという設定。この小説も良かったけどそれよりもっと淡々として、でも心に余韻の残る文章かな。
この小説を読んでいると、子どもが否定しがちな親だってそれぞれの気持ちの揺れやドラマを経験している、自分とさして変わらないひとりの人間なのだなあと愛しくなる。「ゴーゴリ」と名付けられて育った主人公が、父親が亡くなった後にその名前をつけられた意味を知る。そのドラマを知り、その親のその時の心に寄り添おうとするゴーゴリはその時既に彼は成人して離婚していて、親の年代になっているのだ。その「ドラマ」はそのまま人間の死と一緒に消滅することが多いのだろうけど、ふとした瞬間に子どもの目の前に現れたりして、それに触れた子どもに心を揺さぶる何かを残すのだろうな。
そして自分だって自分しか知らないドラマをやはり紡ぎながら生きていっている。小さなこどもたちを育てて働いて、その時々に泡のように浮かんでくる嬉しさや悲しみをそっと自分の記憶に刻印して年齢を重ねていくんだろう。この気持ちがぐりぐらの前に現れる時は来るのだろうか、とも思う。現れなくてもそれはそれでいいのだけどね。
いい小説でした。
■ llcafell at 02.05 ■
Trackback
TrackBack URL for this entry
■■■ http://llcafell.s28.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/974 ■■■
■■■ http://llcafell.s28.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/974 ■■■
Post a comment


