■■■ 2007-01-16 ‖Tue‖ ■■■
 ナイロビの蜂
ナイロビの蜂
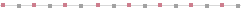

英国の外交官であるジャスティンと共にナイロビに暮らす妻テッサが殺されるシーンが映画のかなり冒頭にあり、時間軸が前後して夫婦の出会い、愛情の深まりが夫ジャスティンの追憶として立ち現れてくる。アフリカでの地元の人々に医療を供給すべく奔走する活動家の妻、対照的に英国伝統のガーデニングを趣味とする物静かな夫。夫婦の間のすれ違いというか、不信の状態から殺された妻の足跡を辿っていくうちに、ジャスティンは妻の気持ちと寄り添い、彼女の愛を確信する訳だが、それと一緒に妻の追っていた国家レベルの陰謀が明らかになっていく。そしてそれと共に自分の身の危険が迫ってくる。
感動作であり、よくできた映画だと思う。見終わった後しばらくは書けなかった。そのぐらいいろいろと自分の巻き起こった感情を反芻してしまう映画。映画評はアマゾンに任せてここでは私の視点からの感想を。
妻テッサの意志、意志が強いという言い方より意志によって生かされているその存在にとても惹かれる。先日「ピアノ・レッスン」を再度観る機会があったのだけど、その主人公であるエイダが「私は自分の意思が怖い。何をするか分からない強い意思が・・・だから行かせて」と夫に言葉を介してではなく伝える場面があったのを思い出した。きっとそのかけらが自分の中にもあるからこそ呼応してしまうのかも。
母である自分としての脳髄反射的な感情の反応に自分ながら驚く。テッサが夫との子を死産で失い、現地の人が入る病院で体を休めながら、隣のベッドの15歳の幼い母が産み落とした(そして彼女はエイズか肺炎で死のうとしている)幼子に乳を飲ませている場面。ジャスティンが陰謀を追って訪れたスーダンの村が他の部族に襲われ、飛行機に医療チームである人間たちは避難するも、伴ってきた可愛がっている現地の子どもはその飛行機に乗せることはできない。その子どもの誇り高い哀しみの表情。ストーリーもさることながら、こういう瞬間の映像が目に焼きついている。
後数時間で震災12年目を迎える。命をしばし考える夜、亡くなられた方の冥福をお祈りします。おやすみなさい。
■ llcafell at 01.16 ■
■■■ http://llcafell.s28.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/1702 ■■■


